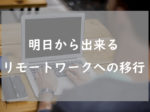- Home
- co-life新着情報, 新型コロナ対策
- 新型コロナウイルス対策(在宅・テレワーク)
新型コロナウイルス対策(在宅・テレワーク)
- 2020/4/14
- co-life新着情報, 新型コロナ対策
〜不動産賃貸管理会社(I社)の取組〜
新型コロナウィルス症(COVID-19)の拡大の状況に鑑み、従業員の安全確保を 最優先するとともに、感染拡大を防止し、有事において賃貸管理業者として社会的責任を果たすべく、以下の対応を講じる事にしました。
【出退社・勤務の対応】
1.従業員は出社前に検温実施し、発熱、もしくは強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)や味覚臭覚障害(味がしない臭いがしない)がある場合には出社を控える
2.従業員の同居者に、発熱が継続するものがいる場合にも出社を控える
3.COVID-19 の罹患者又は濃厚接触者と接点のあった従業員は、外出・出社を控える
4.在宅勤務の積極的な実施
5.公共交通機関での通勤者は、時差出勤・時差退社の実施
6.出社時、帰社時の手洗い、アルコール消毒、マスク着用を励行
7.高齢者への接触営業を控える
8.窓口営業時間帯の変更
新型コロナウィルスへの対策や緊急事態宣言が発令された場合、当社は、時差出勤、就業時間の短縮、営業時間の短縮、在宅勤務、休業命令を発するものとする。中でも在宅勤務を優先させます。
在宅勤務の定義とは、勤務開始を自宅で迎え、勤務終了を自宅で迎えることです。出社の必要は基本ありません。
但し、業務の必要性に応じ、営業先への訪問、自社事務所への用事、業務上必要な取引先への立ち寄り等の外出を認めるが、極力通信機器を介した業務とし、外出する場合は、感染に極力注意した行動をとること。
在宅勤務命令は、会社よりの指示命令とします。
在宅勤務に関して、法的な手続きが求められるわけではありません。ただし、社員の職場環境、労働条件に関する事項ではあるため、就業規則に規定を置くことが望ましいといえますが、今回の当社の在宅勤務では、労働条件の変更は行わず、出社退社場所が会社や店舗を自宅に変更の指示命令を出すだけですので、新たに就業規則に在宅勤務に関する規定を置くことはしません。
労働者にとって不利益変更と解されるおそれが少なく、事前に全社員に周知を行い、これに異議を持つ社員とは個別に同意を取得する等の対応を取ります。在宅勤務の場合でも給与が変わることはありません。
また、出向や派遣社員については、出向元と派遣元企業との間で締結する出向契約や労働者派遣契約において、就業場所が特定されています(労働者派遣法26条1項1号)。そちらに自宅を含む事業所以外の労働環境が指定されていない場合には、出向先や派遣先企業である当社が出向社員や派遣社員に在宅勤務を命じることはできません。この場合、別途、出向元や派遣元企業と協議を行い、在宅勤務に関する合意を取得する必要があります。
なお、働き方改革の一環として改正された労働安全衛生法に基づき、使用者に対して、労働時間の客観的な把握義務が課されています(同法第66条の8の3)。在宅勤務の実施に際しては、PC等を利用して労働時間を管理することとします。
ラッシュアワー回避のため、時差出勤制度を導入した場合の手続については、労働基準法(以下「労基法」といいます)89条1号にあるとおり、始業時刻及び終業時刻は就業規則の必要記載事項となっています(労基法89条1号)。
就業規則では、業務都合による始業・終業時刻の変動が規定されているため、そのような場合には当該規定に基づき、労働者に周知すれば足りることになります。よって時差出勤を会社で決め、該当従業員へ会社より指示命令を行います。
使用者は、労働者に対し、安全配慮義務を負っています。したがって、労働者が安全に労務を提供することができる環境を整えることが出社命令を出す大前提となります。
新型コロナウィルスの事例でいうと、使用者の合理的な配慮義務を尽くし、新型コロナウィルスへの感染リスクを可能な限り排除することが重要です(安全配慮義務の内容については、Q7で詳述いたします)。
以上の義務を使用者が尽くしている限り(使用者が、労働者が安全に労務を提供する環境を整えている限り)、使用者は、労働者に対し、業務命令として出社を命じることができます。
ただし、質問のケース(3)及び(4)については、従業員本人又は家族に新型コロナウィルスへの罹患のおそれが生じており、そのような中で出社命令を発することは、従業員本人のみならず、同じ職場の他の従業員に対する安全配慮義務違反をも構成しえます。したがって、この場合には同命令を発することは避けるべきでしょう。
会社として社員ごとに個別具体的な出勤または在宅勤務の必要性を判断し、異なる業務命令を発すること自体には、特段問題ありません。ただし、使用者は、労働者に対し、安全配慮義務を負っています。したがって、労働者が安全に労務を提供することができる環境を整えるために、使用者の合理的な配慮義務を尽くし、新型コロナウィルスへの感染リスクを可能な限り排除することが出社命令を出す前提となります。
結論としては、いずれの場合においても、就業規則の定めに基づき出勤停止命令を出すことが可能です。そもそも、新型コロナウィルスに罹患している社員は、同感染症が感染症法における「指定感染症」に指定されたことで、同法第18条に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができるようになっています。
なお、労働安全衛生法68条は、事業者に対し、指定感染症に罹患した労働者の就業を禁止する義務を課していますが、この点について厚生労働省は、「感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることとして、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはしません。」としている点に留意する必要があります。
特に、依然として新型コロナウィルスに罹患しているか否かが不明である状況であることから、上記に述べた法に基づく就業制限の対象にはなりません。
しかし、使用者は、職場環境と労働者に関して安全配慮義務を負っており、かつ、職場の秩序維持権限を有するため、就業規則の定めに基づいて、出勤停止命令を出すことができます。
ただし、この間業務に従事できなくなった労働者に対して、賃金や休業手当を給付する必要があるかは別の議論となります。別途Q10をご参照ください。
使用者が労働者に対して負う安全配慮義務は、結果債務ではありません。すなはち、労働者が結果として業務遂行中に新型コロナウィルスに感染したとしても、直ちに使用者による安全配慮義務違反になるというわけではありません。
使用者において、新型コロナウィルスへの感染リスクと感染経路の情報収集と適切な理解、政府を始めとする公的機関が公表する予防方法や対応措置の把握、これらに基づく合理的な衛生上、業務上の措置を科学的、医学的知見・基準に基づいて、適切に履行できているかが重要になります。
[まず、新型コロナウィルスに関する情報を整理すると以下のようになります。]
・無症状の病原体保持者からの感染可能性は低いとされている(症状が最も強い時期に他者への感染可能性も最も高くなる。
・基礎疾患を有する方、高齢者の方、妊婦の方などが重症化する傾向にある。若年層は比較的軽症で済むことがほとんど。
・予防は石鹸による手洗とアルコール消毒が有効。また人混みの多い場所、お互いの距離が十分に確保できない状況で一定時間を過ごす際には注意をすべき。
・感染者の8割は他人に感染させていない(2月26日時点、厚労省発表)。一人の感染者から多くの人に感染が拡大しているケースと、小規模患者クラスター(感染経路が追えている数人から数十人規模の患者集団)の発生ケースがある。
[このような状況を踏まえて、当社が取りうる各種の対応を列挙いたします。]
・濃厚接触を避ける措置(在宅勤務の推奨、30分以上の会議の回避、会議を行う場合の参加者の一定距離の保持(2m以上)及び適時の換気)、TV会議への変更
・石鹸による手洗いとアルコール消毒の推奨
・咳やくしゃみ等の症状のある社員への咳エチケットの周知及びマスク着用の要請
・体調不良の社員に対する休暇取得等の推奨
・感染者の多いエリアへの出張の回避
Q7で述べたとおり、使用者が労働者に対して負う安全配慮義務は、結果債務ではありません。すなわち、労働者が結果として業務遂行中に新型コロナウィルスに感染したとしても、直ちに使用者による安全配慮義務違反になるというわけではありません。
確かに政府はイベントの自粛を要請し、不要不急の外出の回避を要請していますが、企業による事業活動の停止を求めているわけでもありません。使用者に求められるのは、労働者が安全に労務を提供できるための事業所の環境構築であり、Q7で紹介したような合理的な措置を取っている限りにおいては、直ちに安全配慮義務違反とはなりません。
もっとも、たとえば感染が疑われる労働者の出社を許容していたり、感染者の増えているエリアからの帰国者の出社を認めたりするなど、個別具体的なケースで安全配慮義務違反に問われることはあり得ます。
懲戒処分の理由と内容によりますが、一般論として、懲戒解雇等の重い処分を課すことは難しいと考えられます。ただし、当然ながらノーワークノーペイの原則に基づき、欠勤期間の非稼働分の賃金を支払う必要はありません。これを超えて、欠勤したことを理由に減給処分を行ったり、解雇の処分を行うことは違法性を帯びることになると考えられます。
原則からご説明します。
賃金は、労務の提供によって発生する「労働の対償」(労基法第11条)です。つまり、民法第624条第1項にあるとおり、「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができ」ず、これを「ノーワークノーペイの原則」といいます。したがって、労務の提供がない場合、使用者に賃金の支払義務は発生しないのが原則です。
ただし、会社都合による休業や自宅待機命令の場合には、労働者は働きたくても働けず、そのせいで賃金を受け取ることができないという事態に陥ってしまいます。このような場合は、民法上の危険負担の法理(民法536条)によって以下のように整理されます。
②使用者の責めに帰すべき事由によって、労働者が労務の提供をすることができなくなったときは、労働者は賃金を受ける権利を有する。
<感染した方を休業させる場合>
労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
<感染が疑われる方を休業させる場合>
新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。
感染が疑われる方への対応は「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)問28「熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか?」をご覧ください。
これに基づき、「帰国者・接触者相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
<都道府県知事が行う就業制限の場合>
都道府県知事が行う就業制限によって労働者が休業する場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当せず、休業手当を支払う必要はないものの、そのような制限がなされず、使用者の自主的判断で休業させる場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があるということになります。
当然ながら、個別具体的なケースによって「使用者の責に帰すべき事由」があるかは解釈が分かれるところではありますが、労働者の新型コロナウィルスへの感染によって都道府県知事が就業制限を行った場合、使用者の責に帰すべき事由がないというのは一般論として妥当な結論です。
ただし、これは使用者がQ7で述べたような安全配慮義務を果たしていたといえる場合であり、そのような義務が果たされていない中で新型コロナウィルスに感染してしまった場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」(労基法26条)と解されるおそれは否定できません。
では、仮に都道府県知事が就業制限を行っていない場合はどうでしょうか。
上記厚生労働省によるQ&Aの回答を限定的に解釈すれば、このような場合には休業手当が発生するようにも思えます。しかし、新型コロナウィルスに感染した社員を、他の社員への感染を防ぐために休業させることは、「使用者の責に帰すべき事由による休業」(労基法26条)にはあたらないと解するべきでしょう。
<社員が、発熱や咳の症状があるとして、自ら休むことを判断した場合>
労働者が自主的に休業に入っているため、原則として賃金や休業手当の支払義務は発生しません。通常通り、病欠の取り扱いとする、病気休暇制度を利用していただくなどの対応が考えられます。
<事業所で新型コロナウィルスへの感染者が発生し、事業所を閉鎖する場合>
新型コロナウィルスへの感染者の発生、および事業所を閉鎖せざるを得なくなった事由が、使用者の責に帰すべき事由か否かを検討する必要があります。使用者としては、安全配慮義務を尽くしている限り、少なくとも民法536条のいう「使用者の責めに帰すべき事由」にはあたらないといえるでしょう。
そして、現在準備されている特措法等に基づき、新型コロナウィルスへの感染者が発生した場合に、行政から事業所を閉鎖するように指示を受けた場合などにあっては、もはや当該事業所での業務遂行は不可能といえ、封鎖による休業に対しては「使用者の責に帰すべき事由による休業」(労基法26条)にも当てはまらないといえるでしょう。
したがって、賃金及び休業手当の支払義務はいずれも発生しないと考えられます。
始業時刻及び終業時刻は雇用契約又は就業規則において明示されており、これを変更するに際しては、雇用契約上別途の合意を取るか、就業規則の変更が必要です(ただし、前述したとおり、多くの就業規則では、業務都合による始業・終業時刻の変動が規定されているため、そのような場合には当該規定に基づき、労働者に周知すれば足りることになります)。
そのような合意又は変更ができた場合には、ノーワークノーペイの原則から、原則として賃金を支払う必要はありません。
しかし、通常どおりの勤務を続けたいと希望する社員に対して、業務命令として1日あたり2時間少ない労働時間での就業を命ずる場合には、労務提供ができなかった時間の賃金又は少なくとも休業手当を支払う必要があるでしょう(どのような事情で当該命令を出すかによって、使用者の責に帰すべき事由があるかの判断は異なります)。
以上を踏まえ、始業時間を2時間遅らせるという場合は、退勤時間も通常の時刻から2時間伸ばすこととし、旧来の終業時刻以降は労働者の任意の退勤を認めるという運用も考えられます。